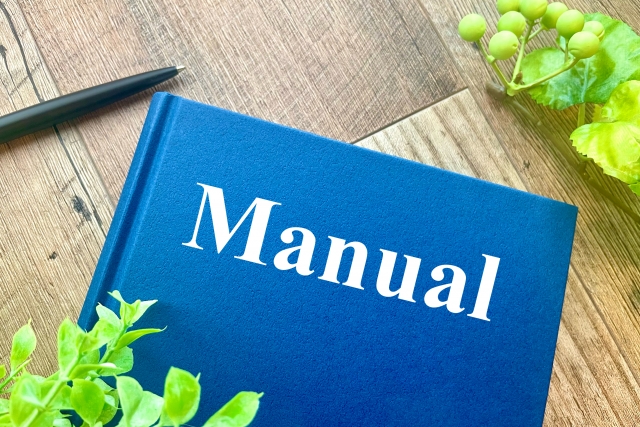近年では、企業が直面するリスクが非常に多様化しているため、企業はリスクマネジメントに取り組む必要性が高まっているでしょう。
リスクマネジメントは企業が存続し成長していくために必要不可欠ですが、構築するためには危機管理マニュアルが重要です。
具体的に何が必要となるのか、解説します。
危機管理マニュアルとは?
企業が活動して成長していく際は様々なリスクに直面することになるため、リスクマネジメントによって顕在化を防止する必要があるでしょう。
リスクの顕在化を防止して、顕在化したリスクによる被害を最小限にとどめるためには、危機管理マニュアルが必要となります。
リスクマネジメントにおける危機管理の対応について、マニュアルとして対応を定めておくことが重要となるのです。
不祥事が起こったり、災害や事故に遭ったりするトラブルの発生は、予期できないことが多いため、予防だけではなく適切な対処も必要となります。
早急に対処できなければ受けるダメージも大きくなってしまうため、予め対応に関するマニュアルを策定しておかなくてはならないのです。
対応をマニュアルとして作成する目的として、自社が営業をするうえでどのようなリスクがあり得るのか、従業員に周知するという点があります。
また、予め危機管理の基本方針や目的、準備、体制、方法などを明確に知っておくことで、リスクが顕在化したときは迅速に対応できるようにするのです。
リスクの顕在化に備えて、危機管理体制において責任者や部署などのそれぞれの役割について、事前に決定しておくことも重要な役割といえます。
緊急時に自社ではどう考えているか、行動の指針は何かを示しておくことで、リスクの顕在時には迷わず行動できるでしょう。
また、緊急時の対応についてあらかじめ定めておくことで、想定している対応に漏れがないかもチェックすることができます。
危機管理に近い言葉として「BCP(Business Continuity Plan)」というものがあり、日本語では事業継続計画ともいうのです。
大災害やテロ、事故、不祥事などが発生して自社にも直接的な影響が起こり、事業の継続が困難になった場合はどうするかを想定し準備しておく計画のことをいいます。
危機管理においては様々なリスクを想定して対応を考えるのですが、BCPの場合は人命を優先し、自社の設備が受ける被害も最小限に食い止めることを目的としているのです。
中枢となる事業が継続できることに焦点を当てて決定していくため、危機管理とは優先する点が異なります。
リスクに対して、事前と事後の対応では企業が取り組むべき危機管理の内容も異なってしまうでしょう。
リスクというのは火種になり得るものであり、燃え上がってはいない状態でも常に存在しています。
何か起こったとき、リスクは発生するのではなく顕在化するものと考えた方が、正確に考えることができるでしょう。
顕在化した場合は、予期せぬ出来事であるインシデントが起こってしまったり、突発的な困難であるクライシスが起こったりすることもあります。
前もって対策しておくことと、発生した場合に被害を最小限に抑えることは、同様に重要な対策です。
予防するための対応と、すでに顕在化してしまってからの対応では内容が大きく異なるのです。
マニュアルに関しては画一的な対応だけを示すのではなく、様々なケースで対応するタイミングごとの対応を定めるのか、一部のタイミングだけにするかの違いがあるのです。
危機管理マニュアルの内容について
危機管理マニュアルは、余分な内容があると必要なときに必要な情報を発見するのに時間がかかるため、使いにくくなってしまいます。
最小限の情報だけを記載するようにしなくてはならないのですが、必要な情報とは何があるのでしょうか?
まずは、危機管理マニュアルを何のために作成したのかという目的などを記す必要があるため、なるべく具体的に記載しましょう。
また、基本方針についても具体的に記載して、必要になった時は誰もが悩まず従えるようにした方がいいでしょう。
対応する責任者や内容を明確にするために危機レベルを設定しておく必要があり、予測される被害規模や被害額を算出してレベル分けをすることができます。
被害額は、例えば製品事故であれば自主回収や製造ラインの停止、取引停止、レビュテーション低下などシナリオを決め、大まかに計算することができるでしょう。
危機が発生した際はすぐにでも対応する必要があるため、初動で迷うことがないように具体策と流れもマニュアルに記載してください。
危機発生直後の行動や対策本部の責任者、設置場所、緊急時のプレスリリース、議事録のテンプレートなどを危機管理マニュアルに組み込むべきです。
災害や事故などのリスクの顕在化の前に復旧へと取り組む必要があるのですが、具体的にどのような取り組みをするべきかを事前に決めておきましょう。
取り組みの内容としては、通信手段の復旧や救援備品の調達や配送、対応に当たることができる社員の把握、被災者への援助などが考えられるでしょう。
危機が発生した場合でも企業を存続させるためには、最低限維持しなくてはならない業務や取引先、顧客の満足を得られるような対応が必要となります。
維持しなくてはならない業務や事業活動レベルについて組織ごとに定めておき、責任者はメンバーに明確な指示ができるようにしておく必要があるのです。
社内で危機レベルや危機の内容ごとに責任者を定めておき、取引先や業界団体、株主などの連絡先も事前にまとめておけば、スムーズに連絡できます。
まとめ
リスクマネジメント体制を構築するには、危機管理マニュアルを定めておくことが重要となるため、企業はリスクが顕在化する前に対策を決めておくべきでしょう。
リスクは常に存在しているものなので、顕在化することを前提として対策を講じておくと、いざ顕在化した時素早く対処できます。
情報が多すぎても必要な情報を見つけるまで時間がかかるため、危機管理マニュアルは完結かつ明確にまとめる必要があるのです。